
ときどき是好日report
2025.12.5 すべては、然るべきところに。感謝を込めて。
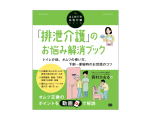 2025年も残すところ、1ケ月を切るところまで来ました。あっという間に過ぎ去った今年1年を振り返ってみると、多彩なことがありました。
2025年も残すところ、1ケ月を切るところまで来ました。あっという間に過ぎ去った今年1年を振り返ってみると、多彩なことがありました。
各地で数々行われた学会や研修会、とりわけ大阪・関西万博会場での排泄についての国際フォーラムは、華やかなメイン会場がおむつのファッションショーで開会式以来の満席になるという大快挙でした。
また8月から朝日新聞 土曜日版に7回連載された「それぞれの最終楽章 : 百寿の母と排泄介護」は私の母の介護を記者の高橋美佐子さんがまとめてくれた記事です。私にとっては、母が亡くなって約2年後に母の介護を見直す、良い機会となりました。そして、その反響の大きさには、本当に驚きました。朝日新聞社にも多くのコメントが届きましたが、私のところにもお手紙や面接、また外来受診など反響が続きました。「介護で最も困ったことが排泄だった」「誰に相談しても解決できなかった」などなど、未だ情報が必要な方に届いていないのだ、という実感と使命を強く再認識しました。
そして本当にタイムリーなことに、それ対する一つの答えとしてこの度、“「排泄介護」のお悩み解消ブック”が出版されます。この本は今年の3月から毎月編集者と企画・執筆者と3人で会議を重ね、作成してきました。この本も私の母の介護を振りかえり、その経験と専門の知識を織り交ぜた内容です。また貴重なケアマネからのアンケート結果も入っています。少しでも在宅での排泄ケアの一助になりたい、という強い思いをもって作成した本で、在宅でご本人もご家族も気持ちよく生活していただきたいという祈りと実践で役立つ情報を込めました。
年末にはなりましたが、連載記事と同じ年に出版できたことは幸せなことだと感謝でいっぱいです。
もしよろしかったら、ご一読いただければ、と願っております。
来る2026年が「全ての人が気持ちよく排泄ができる毎日」となりますように。
2025.9.16 朝日新聞ウイークリー版の連載
2025年7月26日土曜日から、朝日新聞ウイークリー版(土曜日紙面・日曜日デジタル配信)で、私の母の介護についての連載記事7回がスタートしました。
タイトルは「それぞれの最終楽章・百寿の母の排泄介護」です。 私はコロナが猛威を振い始めた2000年から東京と高知の2拠点で生活をはじめ、当時サービスつき高齢者住宅に入っていた母と同居を開始し、3年3か月在宅介護をして最期は自宅で看取りました。
その過程で、介護者として排泄問題に直面し、専門知識と技術を持っていても母娘の関係性ではうまくいかないことが多々ありました。在宅ケアをしている専門職への講義の中で、その話をリアルタイムに伝えていたのですが、反響が大きく、それが連載記事へとつながりました。
記事は朝日新聞記者の高橋美佐子さんが取材して書いてくれたのですが、母が亡くなって2年たった今、私にとっても見直す良い機会となりました。 驚いたのは、反響のすごさでした。
特に第1回めに排泄物の臭いについて書いたところ、「それで在宅介護をあきらめた」、「どのように対処したか知りたい」「あるある、で身につまされた」などなど、たくさんのコメント、そしてお手紙も頂戴しました。
お手紙には、ご自分の大変だった介護経験や、ご自身の辛い排泄障害の相談もあります。
また、以前私が執筆し、ほとんど絶版状態となっていた「パンツは一生のともだち」という単行本が私の名前と一緒に一行紹介されていたのですが、出版元・現代書館の社長から「在庫がなくなったから、そちらにあれば送ってほしい」というお電話を頂戴しました。一気に70冊売れたそうです。世の中に困っている人、助けを求めている人が実にたくさんいることを再度実感し、まだまだやるべきことがたくさんある!と強烈に感じています。
これは母からもらった最後の宿題として、しっかり果たそう!と思っています。
2025.5.12 精密栄養学
新しいことを学ぶのは、とても楽しいことです。2月14、15日に横浜パシフィコで開催された第40回日本栄養治療学会(The Japanese
Society for Parenteral and Enteral Nutrition Therapy: JASPEN)に発表演題をもって参加しました。
1万人以上の参加者があったマンモス学会の副会長は、私のランニング仲間の斎藤恵子さんで、素晴らしい学会を開催されたことに尊敬の念を深く持つと同時に、自分のことのように心から嬉しかったです。(写真は学会会場で斎藤さんとご一緒したもので、企業のマスコットを抱いています)
学会は内容的にも、とても充実していました。私が10年以上前から深く興味を腸内細菌のことは随所でプログラムが組まれ、興味を持つ人が大変多いことに驚きました。そしてそのプログラムの中で「精密栄養学」という言葉を初めて知りました。文献では「精密栄養(Precision
nutrition)とは、遺伝的因子などの内的因子に加えて、生活習慣や腸内細菌などの外的因子の影響も考慮に入れ、健康を維持するために必要な栄養学的情報を各個人の体質や生活スタイル、ライフステージなどに応じて提供するものであり、日本語では個別化栄養や精密栄養などと訳され、次世代の栄養学として注目されている。(「精密栄養学」概論:我々は何を食べたらよいのか?
:重城喬行他 実験医学Vol.41 No.10 2023)となっています。つまり同じ物を食べても太る人もいれば、痩せる人もいたり、体に良いという食品の効果が出る人もいれば、全く効果がない人もいるというのが、現実的な精密栄養の表れだと思います。精密栄養学が注目され始めた背景には、遺伝子解析や腸内環境の解明、健康ビッグデーターなどの研究が発展したからこそ、次のステップに入ったのだと、学びました。
ライフスタイルという言葉があります。英語でLifeには、命、生活、人生という3つの意味があります。
食べた物が命を維持し、時には奪い、食べた物がその人の日々の心身を創り、そして人生を織りなしていきます。排泄を専門としている私ですが、以前から食と排泄は一つのこととしてとらえてきました。今、「精密栄養学」を知り、食と排泄は自分らしくどう生きていくかを表現している1つなのだと、確信しています。
2025.1.9 2025年がスタートしました。
2025年がスタートしました。昨年はお正月から北陸の大震災、羽田飛行機事故と続き、大変な年明けでしたが、今年は穏やかなスタートでほっとしております。元旦のニュースインタビューで震災にあった方々が「普通が一番」「当たり前の日常生活がとても幸せ」と異口同音におっしゃっていたことに今も続くご苦労がしのばれ、心に沁みました。
「当たり前にできることの幸せ」これは何でも当てはまると思いますが、特に排泄は当てはまります。改めて災害グッズを確認しました。実家の納戸に残っていた亡くなった母のおむつはお世話になったディケアにお届けするつもりでしたが、万が一の災害のために残すことにしました。集尿器も改めて洗浄しなおし、きっちり箱に収めることにしました。使う日が来ないことを願いつつも、断捨離して良い物とそうでない物を見極めるのに災害への覚悟がいることを実感した年明けです。
さて、私の今年はどんな一年になるだろうか、とワクワクしてシステム手帳を見ます。 3月までの外来を除く予定として、 NPO日本コンチネンス協会のセミナー講師や講演会が合わせて8日間入っています。日本栄養治療学会での発表、その他の講演会が5回、フルマラソンが2回です。フルマラソンは12月1日に予定していた那覇マラソンは足指骨折して出走できなかったため、1からの調整が必要で、ちょっと気合がいります。
来年度として4月からの予定としては、研究予定が3つ、一般単行本出版、昨年出版された便失禁ガイドライン2024の英語版の発刊。これは現在作業が進行中です。
そして関西万博で国際おむつフォーラムが予定されており、現段階での概要は以下です。
・ 開催日時:2025年6月25日(水)13時~17時
・ 開催場所:フェスティバル・ステーション(大阪・関西万博会場内)
・ 参加規模:300〜350名 トピックスは以下の3つになります。
1. 国内外のおむつについて
2. おむつのリサイクルとサステナビリティ
3. おむつのアクセシビリティ
これから詳細が決まっていくと思いますが、万博に参加予定の方は、ぜひこのフォーラムにあわせて予定に入れてください。
2025年はよく学び、良い仕事をし、よく遊び、大きく笑い、気持ちよく走り、たくさん料理して、おいしく食べて、気持ちよく排泄して、良い夢みてぐっすり眠り、その時を一生懸命によく生きようと思っています。欲張りですね!自分でもそう思います。でもそれを思え、当たり前にできることに深く感謝する気持ちを何より強く持ちたいと思っています。
今年も、なにとぞ、どうぞよろしくお願いいたします。
2024.7.1 排泄ケア関連学会
一年中、何かしら学会は全国各地で開催されていると思いますが、私(西村かおる)が関係する学会は5月、6月に集中しています。
今年私が参加した学会は以下のとおりです。
5月17 日・18日 第37回日本老年泌尿器科学会 大会長:原勲(和歌山県立医科大学泌尿器科教授)
メインテーマ「Diversity in Geriatric Urology」 会場:歌山城ホール
5月25日・26日 第33回日本創傷・オストミー・失禁管理学会
大会長:田中マキ子(山口県立大学学長) メインテーマ「煌めくWOCNの力」 会場:海峡メッセ下関
6月15日・16日 第25回日本認知症ケア学会 大会長:諏訪さゆり(千葉大学大学院看護学研究院)
メインテーマ「AI(人工知能)を認知症ケアに生かす」会場:東京国際フォーラム
6月25日・26日 第28回腸内細菌学会 大会長:藤田史郎(日精ファルマ株式会社取締役・健康科学研究所所長)
メインテーマ「腸内環境研究が拓く健康社会~最新研究の動向と社会実装に向けた取り組み~」
会場:タワーホール船堀 学会は最新情報を提供する場でもあります。
各々の学会長が選んだテーマを見ても、それが実感できます。ダイバーシティや、AIは一般社会でも広がり、注目を浴びている言葉です。そして腸内細菌はそのものが、今では一般社会の健康ブームの中心です。10数年以上前の腸内細菌学会で発表される演題は、ほんどがネズミの実験研究で、私は満足に理解できず、場違いにいると思い続けてしました。しかし昨今は、今回のテーマに組み込まれた「社会実装」という言葉にふさわしく、人の健康に関する疫学調査や臨床応用のテーマも多く、やっと求めていた学会となった!と本当にうれしい学びの場となっています。
また印象に残ったことの一つは、第37回日本老年泌尿器科学会、第33回日本創傷・オストミー・失禁管理学会では、偶然にも各々の地元酒造の若手代表取締役の講演があり、大変興味深いお話が聞けたことです。和歌山県では、平和酒造株式会社・山本典正代表取締役が「ものづくりの理想郷~日本酒業界で今起こっていること~」、山口県では、旭酒造株式会社・桜井一宏代表取締役が「獺祭について~現代だからこその伝統的なモノ造り~」というテーマでお話くださいました。お二人とも酒蔵元の長男として生まれても、大学卒業後は全く異なる分野に就職し、結局はあとを継いだという共通点があります。お二人の方法は大きく異なりますが、古い伝統・しきたり・技術がとても強く残る酒造の世界で、紆余曲折、挫折・失敗の中でも海外進出を目指し、まだまだ発展している現在進行形のストーリーは、ドラマよりドラマチックでパワーをたくさんもらったことも共通していました。
地方での学会の楽しみは、豊かな食と歴史、文化に触れることはもちろんです! コロナが明けきった今年は、久々に、はばかることなく、おいしい地のものを堪能し、そして大いに歓談しまくりました。また趣味である神社巡りも日本神社100選のうちの3か所も巡ることができ、とても、とても幸せな学会巡りでした。